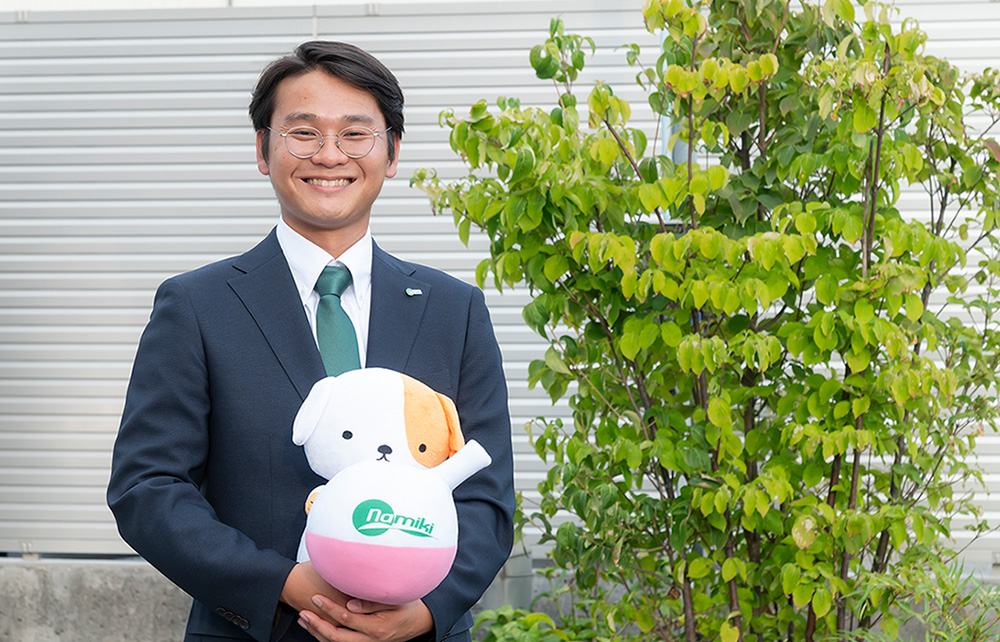
高校時代、私はSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定された高校に在籍していました。大学と提携して微生物の研究を行う機会があり、その経験から、生物系の学科で学びたいと思うようになりました。理系で生物を扱える学部としては、農学部や理学部、工学部などがあげられますが、その中でも公立である富山県立大学を選びました。
高校では、キイロタマホコリカビ(いわゆるカビ)を使った研究を行いました。カビが餌を探して自ら動き、胞子を高く放出して増えていく様子を観察して、「生き物って面白い」と感じました。餌を与えるとその線に沿ってカビが動く実験もあり、こうした観察を通じて、生物の面白さをより身近に知ることができました。
大学では、生物工学科での学びとして、大腸菌を使った研究を経験しました。大腸菌が作るもの(酵素)を増やす研究などを通して、理論は理解できるものの、微生物の過程は目に見えないこともあり、変化の捉え方や考え方を深めるきっかけになりました。また、遺伝子改良などの実験を通して、理論と実際の生き物の動きの違いを体感できたことも、貴重な学びとなりました。
学業以外では、茶道部にも所属しました。当時、男子が多い環境でしたが、部員を増やすために勧誘活動を頑張り、実際に新しい部員を迎えることができました。また、茶道を通じて学んだわびさびや静けさの感覚も、人生の幅を広げる経験となりました。
現在は県内の企業である商社で営業職として働いています。最初は営業という職種にあまり興味がなかったものの、やってみると非常に面白く感じました。
今の仕事の面白さは、計画通りにうまくいくときも、予想外の結果になったときも、どちらの経験も次に活かせる点にあります。お客様の背景を考えて戦略を立て、ビジネスプランを提案するプロセスが特に楽しいと感じています。
現在の会社では、試験薬を主に扱っています。お客様は大学、企業、病院など、理化学の実験を行う機関です。ワクチン製造企業や病院で使用される検査部材なども扱い、生物工学科で学んだ知識が大いに役立っています。お客様の背景を理解し、これから必要になるものを予測して提案できることも強みです。
富山県立大学は公立大学ながら非常に整った学習環境があります。社会に出て他の大学と比較すると、研究設備や材料など、学びに使える資源の充実度が際立っていることに気づかされます。
大学での経験や学びは無駄になることはありません。自分なりに興味を見つけ、学びを積み重ねることで、それが将来の仕事や人生に生きていくと思います。
