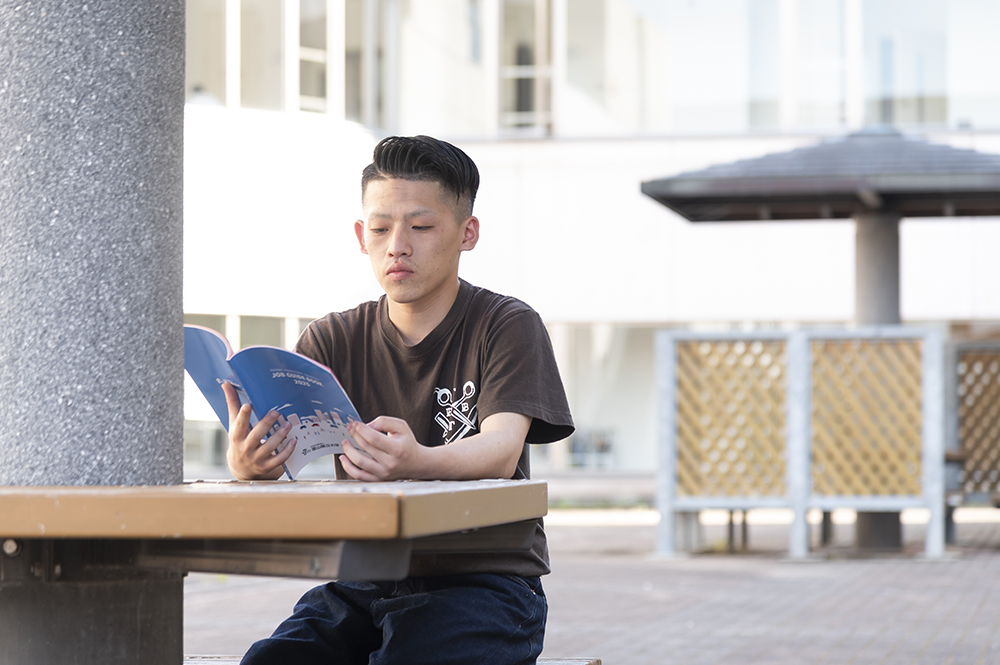富山県出身ということもあり、進学にあたって県外へ出たい気持ちは特にありませんでした。工学部を選んだのは、もともとものづくりに興味があったからです。ただ、当時は進みたい分野がまだ明確には決まっておらず、「機械・電気・情報」の3分野を幅広く学べる知能ロボット工学科なら、将来の選択肢を広げられると思い志望しました。
オープンキャンパスにも参加し、それまで持っていた“工学部=閉鎖的”というイメージが大きく変わりました。棟も新しく、学科の説明や特色ある授業の紹介などを通して、「意外と明るい雰囲気なんだな」と感じたのを覚えています。
実習の種類が多く、プログラミングや工作機械の操作など、幅広い体験ができる点が魅力です。特に、実際に手を動かして学べる授業では、旋盤を使って印鑑ケースを作るなど、ものづくりの楽しさを実感できました。
また、学生同士の関係性もとてもよく、課題やテスト勉強は仲間と協力しながら取り組むことが多かったです。自然と友達ができて、「みんなで単位を取ろう」と声をかけ合って支え合える雰囲気がありました。
大学院は、誰もが進学するというイメージはありませんでしたが、「行けるなら行って、自分の可能性を広げたい」と思い、進学を決めました。学部時代には見えづらかった研究の目的や終着点も、大学院での学びを通して少しずつ理解できるようになってきたと感じています。
現在は、小さな歯車をつくる「スカイビング」という加工技術に関して、超音波を活用することで、工具の摩耗を抑えたり製品の精度を向上させる研究に取り組んでいます。実際に加工しながら課題を見つけ、解析・改善を重ねる日々です。こうした技術はEVの自動車やロボットなど、幅広い分野の品質向上に活かされる可能性があります。
今後は、国内学会・国際学会での発表も控えており、論文提出やプレゼン準備にも取り組んでいます。人前で話すのは得意ではありませんが、さまざまな場所へ行き、多くの人と関わる経験はモチベーションにつながっています。
私の地元・八尾では「おわら風の盆」という伝統行事があり、小さい頃から毎年参加しています。母のおなかの中にいるときから唄を聞いていて、歩けるようになったら自然と踊り出すと言われるほど、地域に根付いた文化です。
最近では、富山市がニューヨーク・タイムズの「2025年に行くべき旅行先」に選ばれたことに関連して、ニューヨークのジャパンパレードに招待され、現地で踊るという貴重な経験もできました。どんな反応をされるか不安もありましたが、現地の方々も興味深く見てくださり、身振り手振りで一緒に踊ってくれる人もいて、とても楽しい思い出になりました。
私は推薦入試で進学しました。受験に向けては数学と英語の基礎をしっかり固め、部活動など高校時代に頑張ったことも、面接でアピールしました。そうした経験も評価につながると思います。
もし進路が定まっていない人がいたら、知能ロボット工学科はとても良い選択肢だと思います。入学後に「機械・電気・情報」の3分野を学びながら、自分の得意や興味に合った道を見つけていけば大丈夫です。
私自身は、電気や情報よりも機械系の分野に魅力を感じて進みました。実際に形に残るものを作れるのが面白く、「ものづくりをしている」という実感が得られるのが好きです。
また、研究室には1人または2人で1台の工作機械が割り当てられるなど、設備もとても充実しています。自分の手で実験や加工を重ねながら学べる、恵まれた環境だと思います。