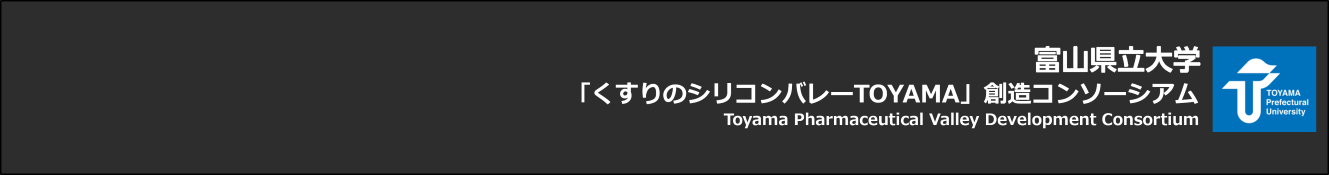国際会議・トップレベル人材・その他の事業
1.トップレベル人材の招へい
 |
 |
 |
 |
元ロッシュ・ダイアグノスティックス副社長 |
独)ビーレフェルト大学 教授 |
仏)国立応用科学院(INSA) 教授 |
仏)国立応用科学院(INSA) 教授 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
瑞)バーゼル大学 教授 |
京都大学高等研究院 |
米)国立衛生研究所(NIEHS/MIH) |
ナノキャリア株式会社 取締役監査等委員 |
東京理科大学薬学部薬学科 |
-
2022年度 招へい予定トップレベル人材・招へい活動
2021年度招へい トップレベル人材・招へい活動
2020年度招へい トップレベル人材・招へい活動
新型コロナ感染症拡大の為、招へい計画はすべて中止
2019年度招へい トップレベル人材・招へい活動
- 1. 11月27日 ― 11月29日 橋田 充 氏
- 2. 10月30日 ― 11月14日 Dr. Ulrich Behrendt
- 3. 09月19日 ― 10月12日 根岸 正彦 氏
- 4. 03月10日 ― 03月14日 Prof. Magali Remaud-Simeon
- 5. 08月26日 ― 10月26日 Prof. Harald Gröger
- 6. 07月29日 ― 07月31日 橋田 充 氏
2018年度招へい トップレベル人材・招へい活動
- 1. 03月25日 ― 03月29日 Prof. Jörg Huwyler
- 2. 03月10日 ― 03月14日 Prof. Pierre Monsan
- 3. 03月10日 ― 03月14日 Prof. Magali Remaud-Simeon
- 4. 03月04日 ― 03月15日 根岸 正彦 氏
- 5. 02月05日 ― 02月25日 Prof. Harald Gröger
- 6. 12月11日 ― 12月13日 橋田 充 氏
2.国際会議
酵素活性分子国際会議2022
Active Enzyme Melecule 2022
| 開催期間: | 2022年9月30日(金) - 2022年10月1日(土) |  HP(PDFでの閲覧) homeのページから 各項目の詳細をご覧いただけます |
|
| 開催場所: | 公立大学法人 富山県立大学 〒939-0398 富山県射水市黒川5180 TEL.0766-56-7500 FAX.0766-56-6182 AEM2022は対面・Zoomのハイブリッド式で開催しました。 |
||
| トピックス: | ・New molecular biological techniques for protein design and engineering. ・Computational tools for enzyme discovery and design. ・The design and development of bioprocesses for the production of (fine) chemicals and pharmaceuticals, and new cascade reactions & combination of reactions. ・Medical biotechnology; antibodies and metabolic engineering for bio-production. |
||
| 議長: | 富山県立大学工学部生物工学科 浅野 泰久 教授 | ||
 クリックで拡大 |
|||
| AEM2022 公式HP | Active Enzyme Molecule 2022 | ||
第1回日本・ドイツ・スイスバイオテクノロジー会議
1st Japan-Germany-Switzerland Workshop for Enzyme Technology and Bioprocess
Development
| 開催期間: | 2019年9月10日(火) - 2019年9月12日(木) |
 HP(PDFでの閲覧) homeのページから 各項目の詳細をご覧いただけます |
|
| 開催場所: | 立山国際ホテル 〒930-1454 富山県富山市原45 |
||
| トピックス: | ・Enzyme Technology ・Screening for enzymes and Directed evolution ・Protein engineering and In-silico design ・Bioprocess Development for Fine Chemical Production ・Medical Biotechnology (Antibody and Bio Pharmaceutical Production / Bio Therapy) |
||
| 議長: | 富山県立大学工学部生物工学科 浅野 泰久 教授 | ||
 クリックで拡大 |
|||
3.実験ノートセミナー
-
2022年度開催
2021年度開催
- 第7回 12月24日 研究室に配属された学生(学部3年生)- 日本語
- 第6回 12月23日 研究室に配属された学生(学部3年生)- 日本語
2020年度開催
- 第5回 12月3日 5プロジェクトに関わる研究者・大学院生 - 英語
- 第4回 9月28日 5プロジェクトに関わる研究者・大学院生 - 英語
- 第3回 9月28日 5プロジェクトに関わる研究者・大学院生 - 日本語
- 第2回 9月17日 5プロジェクトに関わる研究者・大学院生 - 英語
- 第1回 8月28日 5プロジェクトに関わる研究者・大学院生 - 日本語
4.研究環境整備(機器共有)
設備共用
(「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアムHP "設備共用")