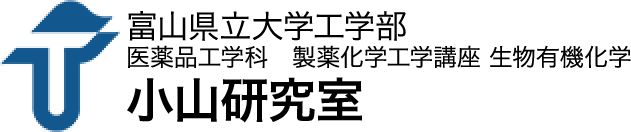製薬化学工学講座 生物有機化学
有機化学による有用物質の創製
1) 未踏領域分子の新合成法の開発、2) 合成法の効率化、3) 分子の特性・動的挙動
糖鎖長を自在に制御可能な糖鎖グラフト法と配糖体型ナノキャリアの開発
糖鎖化学は生命科学のフロンティアにあります。今日までにグリコシルドナーが数多く開発され、特定のドナーのみを選択的に活性化するための合成戦略が提案されています。しかし、多糖配糖体の合成は未だに難しく、多大な労力と熟練した技術が必要です。
こうした背景の下、最近、私たちは任意の骨格から糖を簡便に伸長させる重合技術:糖鎖グラフト法を開発しています。環状サルファイト型の糖モノマーを用いる手法であり、アグリコン上の水酸基を開始剤としてMS
3Aの存在下で酸を作用させると、SO2の脱離に伴う重合が進行し多糖配糖体がワンポットで得られます(上図のA)。開始剤とモノマーの仕込み比により糖鎖長を自在に制御できる点も特徴であり、生理活性物質の誘導体や機能性ナノキャリアの合成に抜群の威力を発揮します。
ケルセチン配糖体(B)からなるミセルはゲスト分子を内包し、高pHではフェノール性水酸基の脱プロトン化とイオン反発によりミセルが崩壊します。α-ガラクトシルセラミド多糖配糖体(C)からなる自己組織体のモルフォロジーは糖鎖長に依存し、N=0ではミセルを、N=2~6ではジャイアントベシクルを形成します。N=1の時は温度変化によりミセル-ベシクル転位が進行することを明らかとしています。
ペプチドの交互共重合法と新機能ペプチド材料の開発
持続可能な開発目標の観点から、環境循環型の新素材として構造タンパク質の高い関心が集まっています。例えば、鋼より丈夫な蚕の糸の主成分「フィブロイン」、脊椎動物の柔軟な皮膚を構成する「エラスチン」、「コラーゲン」、昆虫の腱の成分で天然ゴムを凌ぐ超弾性の「レシリン」は特定のアミノ酸配列の繰り返し構造を持つことが知られています。これらはアミノ酸配列を合理的に設計し、その配列を繰り返すことで様々な物性を示す構造材料を開発可能であることを示唆しています。。
嵩高い置換基を側鎖に規則配列させたペプチドに対し、ずり応力を添加すると強接着性が発現することを見出しました(B)。解析の結果、応力によりペプチドが伸びきり鎖に変化すること、伸びきり鎖の構造緩和が嵩高い置換基により速度論的に抑制されること、応力方向に沿ってマイクロファイバーを形成し、その絡まり合い(物理架橋)により界面間が強く接着することを明らかとしています。
外部刺激によってペプチドの高次構造を合理的に制御する研究にもさらに取り組み、α-メチルフェニルアラニンとα,α-ジアルキルアミノ酸を交互に配列することで、溶媒の極性変化によって310らせん構造と平面状のC5構造とをスイッチするようなペプチド型のフォルダマーの開発にも成功しています(C)。
分子集積・連結を簡便化するニトリルオキシド反応剤の開発
中分子量のビルディングブロックの自由自在な分子集積・連結を可能とする様々なニトリルオキシド反応剤を創出しています。 ニトリルオキシドは高反応性の1,3-双極子であり、様々な不飽和結合と無触媒で付加反応が進行します。しかしその反応性の高さ故に化学的に不安定であり、単離することは難しいです。一方でニトリルオキシドの周辺に嵩高い置換基を導入すると、分解反応が速度論的に抑制されて安定に単離可能になります。私たちは安定ニトリルオキシド反応剤として、i)
2官能性ニトリルオキシド、ii) オルソゴナル反応剤、iii) 高分子ニトリルオキシド反応剤、iv) 撥水剤、v) 蛍光プローブなどを開発し、これらを用いた有機中分子の無触媒反応と合成分子の機能について報告しています(下図)。